 |
1「善福寺(ぜんぷくじ)とサルスベリ」(丸ケ谷町内) |
|
浄土真宗本願寺派の仏教山善福寺は、文明11年(1479)太田道潅の子孫教山坊により、中之嶋に創建された。寛永年間(1624〜1644)、斐伊川の洪水により流失し、上之郷堂保に移転、さらに貞享元年(1684)現在地に移り、享保20年(1717)には本堂が再建されている。
境内にはサルスベリがあり、幹胸高周囲1.75メートル、樹高5.2メートル、樹幅6.3メートル、樹齢二百年前後もある古木が見ものである。 |
(パンフレット「上津見てあるきー斐伊川が育てたロマンー」から)
|

|
2「西円寺とサルスベリ」(奥井谷前町内) |
|
|
浄土真宗本願寺派の施尾山西円寺は、元徳元年(1329)、佐々木高網の孫教順坊により天台宗天正院を改修して中之坊と名づける。その後、現在地に浄土真宗本願寺派西円寺と改め現在に至る。
境内には白、赤、挑、紫色の花をつけるサルスベリがあり、中でも白花は幹胸高周囲1.2メートル、樹高9.5メートル、樹幅7メートルもある。赤花は株元で4本に分かれており、地際周囲は白と同じ1.45メートルの
見事なものである。
|
(パンフレット「上津見てあるきー斐伊川が育てたロマンー」から)
|
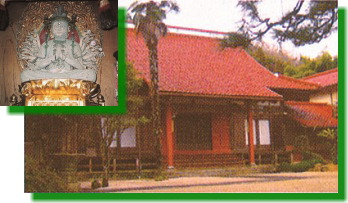 |
3「上乗寺と千手観音坐像」(大谷町内) |
|
曹洞宗天徳山上乗寺は、もと真言宗に属していたが、文明年間(1469〜1487)理観和尚により改宗して禅規を開いた。宝暦4年(1754)の記に抱寺9、辻堂7とある。
出雲市の指定文化財である千手観音坐像があり、像高1.03メートル、幅0.72メートルでヒノキの寄木造りとなっている。鎌倉時代興正菩薩の作といわれる。
参道には、樹齢釣300年位で、直径1.7メートルと1.2メートルの杉の巨木二本のほか、直径1.3メートルのシイの巨木がある。 |
(パンフレット「上津見てあるきー斐伊川が育てたロマンー」から)
|
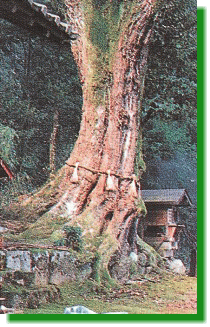 |
4「安楽寺と荒神さん」(大谷町内) |
|
言宗醍醐派の嶺照山安楽寺は、昔は五山あって、安楽寺をもって寺名とし、他の四寺を末寺としていた。国家鎮護、郷内隆昌の祈祷所として隆盛をきわめたが、時代の推移とともに末寺を失い、安楽寺も火難にあって現在地に移った。
境内には樹齢を重ねたシイの巨木があり、荒神さんの木として祀られている。
|
| (パンフレット「上津見てあるきー斐伊川が育てたロマンー」から) |
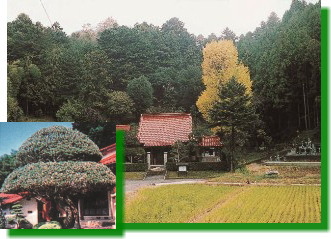 |
5「正善寺とモッコク」(船津上ゲ町内) |
|
浄土真宗本願寺派の妹尾山正善寺は、尼子家臣妹尾源十郎、赤名の西蔵寺で仏門に入り、明応6年(1497)船津に高倉山正善寺を建立する。
安永3年(1774)斐伊川の洪水に遭い現在地に移転、のち、山号を妹尾山正善寺と改めた。
境内には、幹胸高周囲1.7メートル、樹冠7.6メートルの樹齢約300年、県内でも最大級のモッコクがある。 また、樹齢が300年くらいのイチョウの巨木もある。
|
| (パンフレット「上津見てあるきー斐伊川が育てたロマンー」から) |
 |
|

