 |
|
1 遺跡や歴史のあしあと |
| 2 五つのお宮と伝説 | ||
| 3 五つのお寺と文化財など | ||
| 4 豊かな四季と景観 |
 |
1 西谷町内に鎮座する「真幸社」(まさきのやしろ)です。 氏子は、西谷町内の住民です。 |
|||
| 祭神は大国主神(おおくにぬしのみこと)(出雲大社分霊)。明治32年(1899)ごろ西谷町及び付近に伝染病が流行したので、町内有志の提唱で、神徳によりこれを防ぎたいと出雲大社の分霊を勧請して信仰した。その後、現在地に祠(ほこら)を建て「真幸社」と命名、昭和23年(1948)拝殿の改築、鳥居建立、神社形態様式に整えた。 例祭日は、11月1日。 |
||||
| (パンフレット「上津見てあるきー斐伊川が育てたロマンー」から) |
||||
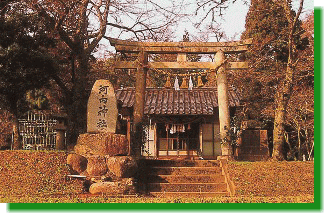 |
2 延畑町内に鎮座する「河内神社」(かわちじんじゃ)です。 氏子は、延畑町内の住民です。 祭神は、木花開耶姫命(このはなさくやひめのみこと)である。出雲国風土記にも記載があり、河内郷の総社であった。 申し伝えによれば、畿内の河内より勧請したので河内明神と称していたという。斐伊川の洪水の時に畑総本家(屋号宮脇)が守護神として、居宅近くへ鎮座したとも言われている。明治44年(1911)上郷神社に合祀されたが、昭和23年(1948)旧鎮座地に奉還再建された。 例祭日は、11月1日。 (パンフレット「上津見てあるきー斐伊川が育てたロマンー」から) |
|||
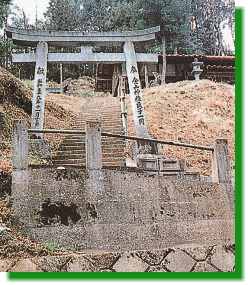 |
3 和久輪町内に鎮座する「金山神社」(かなやまじんじゃ)です。 氏子は、和久輪町内の住民です。 祭神は、金山彦之命である。創立は不詳なるも、古老の伝えるところによれば、「応仁年中(1467〜1469)の創建で、後に弘治年中(1555〜1558)上之郷城主祈願のため改造再建したものである」という。明治44年(1911)上郷神社に合祀されたが、昭和23年(1948)旧鎮座地に奉還再建された。 例祭日は、11月5日。 (パンフレット「上津見てあるきー斐伊川が育てたロマンー」から) |



